今年は3月から体力測定を兼ねて山歩きしている。
昨年から体力が落ちたと感じる経験が増え出した。
山歩きや早朝の軽ランニングの時に衰えを感じる。
ただランニングはその時々で調子に波がみられる。
私はスマートウオッチでランニング記録している。
記録を見ると以前より劣ってきた事が一目瞭然だ。
但し以前と同程度の記録が時々だが出る事もある。
走っている時に調子が良いと感じると記録も良い。
この稀に起きる好調状態を出来れば増やしたい。
老化には抗えなくても好調が増えたら嬉しい。
様々な事を考えて試しつつ運動を続けている。
今回は三角岳~大毛無山の残雪期縦走登山の報告。
1 登山計画
ここ数年は毎年残雪期に三角岳~大毛無山を歩いている。
このルートは稜線歩きが魅力で少し長距離だが春のお楽しみ。
一方で老化と共に完歩できるか徐々に不安も感じている。
昨年は特に積雪後に出かけた際雪が足に沈み相当苦労した。
このため今年は積雪負担の少ない時を狙い登山計画した。
一方で日々積雪減少し悪天候が続くと登山時期を逸する。
4月上旬で天気に恵まれそうな日は4月5日ぐらいだった。
幸い気象庁の降雪情報サイトで積雪影響は少な目と予想した。
当日天気予報は良好で山頂付近の風速10mも想定内と捉えた。
この日以外は天気不良が続きそうなため登山に行く事にした。
2 登山概要
4月5日(土) 天気 晴、弱~強風(山頂)、気温5~10℃
みちのく有料道料金所手前から登山スタート。
東北電力鉄塔のあるゲート脇から林道に入る。
除雪林道を進んだ後に未除雪の唐沢林道へ左折。
積雪の低い所を選び平均積雪1mの雪上に登る。
最初は林道を約2時間歩くが緩い斜度は基本的に楽。
しかし沢筋沿いは冷え込み難いためか雪質軟弱傾向。
当日は平均5cm前後雪に足が沈んで負担感があった。
林道を分かれて尾根筋に変わる頃から雪質も変化。
林道から尾根へトラバース歩行になると新雪感出現。
あくまで推測だが登山前数日の天気を予想してみた。
林道区間は濡れ雪か弱雨で尾根筋は小雪の可能性。
ただ新雪も多くはない様で足への負担はキツくはない。
この後新雪傾向は山頂まで続き積雪3~8cm程と感じる。
今回は三角岳ルート中で計3度野生動物の痕跡・遭遇あり。
最初は林道の終盤で熊と思われる足跡を見つけた。
この区間では4年前も熊と思われる足跡を見ている。
また標高628の前後でカモシカを計3頭見かけた。
最初は628の手前を登攀中に2頭の連れカモシカ遭遇。
次に628の先で単独1頭のカモシカと遭い写真撮影。
今回の三角岳登山は過去比べ積雪量は相当多かった。
三角岳で昼食休憩した後45分ほど歩いて大毛無山着。
大毛無山で約10分休んた後は駐車地点に向け下る。
下りルート中の最難関は標高734地点の通過。
標高734は樹木密集地帯で樹木上に残雪が付着する。
樹木上の残雪量が多ければ樹木上を歩いて通過する。
だが樹木上の積雪が少なければ通過できず下を巻く。
今年は積雪が多いので\樹木の上を歩けると期待した。
だが734に着いてみると残雪量は予想より少なかった。
それでも行けると判断し樹木上の残雪に向かった。
イザ進んでみると残雪が傾斜していて歩き難い。
更に残雪を踏み抜き残雪が崩れる不安感に襲われる。
マズイと感じ雪の上を這い歩きで荷重分散を心掛ける。
雪崩れせず何とかピークに到達した時は心底安堵した。
標高734以後は特に大きな支障もなく下山出来た。
下山の最終地点に近づくと残雪がほぼなくなる。
ヤブ道に変わったが余り煩くなく歩行に支障はない。
雪のないヤブを下り終える直前にはまた残雪が出現。
標高678や734など西向き方向は雪が消え易いと感じた。
一日を通し地形や方向で雪の差を様々感じさせられた。
この日は動物や地形と自然の関係を考えさせられた。
毎年同時期に登山する面白さの一面を知る事ができた。
3 登山後の私見
(1) 動物の習性
この日はカモシカを目撃し熊らしき足跡を見つけた。
カモシカの目撃地点は3年前の登山時とほぼ同じ場所。
熊らしき足跡の目視場所は4年前の登山時とほぼ同じ場所。
残雪期の野生動物は稀少なエサ探しに必死だと推測する。
カモシカは残雪の中でも雪解けの早いヤブ周辺で目撃した。
熊の足跡は山側から沢側へ下る方角に足跡が残っていた。
どちらもエサを求めて移動する中の目撃と私見推測した。
考えてみれば私も他人も同じ様な行動をしていると思う。
私は春になると自分だけ知る場所に出かけ山菜採りをする。
人も動物も何時何処に行けば食物があるかを身体で覚える。
私が見た動物の行動も毎年繰り返される動物の姿と捉えた。
(2) 積雪に関する推測
今年は3回残雪期の山を歩いたが3回共苦労があった。
今回は前の2回より楽だったが3回共雪に足が沈んだ。
雪に足が沈む割合が深いほど足への負担が大きい。
既に市内の積雪は0cmで市内と山では積雪に大差がある。
現地に行かないと現地の雪の状況は分からない。
何とか現地に行く前に現地の雪状況を推測したい。
そこで昨年から気象庁の積雪データを参考にしている。
登山予定の山の積雪情報が直接分かるデータはない。
そこで似た標高の場所の積雪を参考にしようと考えた。
今回の三角岳登山口はみちのく有料料金所で標高約175m。
その標高と似ている青森近郊の観測点は青森大谷観測点。
青森大谷は青森空港がある場所で標高は190m。
場所は少し離れるが標高はほぼ同じで参考になりそう。
因みに三角岳付近に大和山観測地点もあるがデータ量少。
気象庁の情報サイトでは大和山の方は降水量しかない。
登山前に大谷の積雪状況を見ると過去4日で累計積雪2cm。
これなら大丈夫と考え登山したが実際は想定より多かった。
登山後に前月分も含め調べたら過去7日間で積雪は累計10cm。
また参考に大和山の降水量を調べたら過去7日間降水量60mm。
因みに同じ7日間の期間の大谷の降水量は10mmで差は大きい。
要は三角岳周辺はそれなりに降雪があったと思われた。
大谷の降雪データは参考にしても完全に当てにはできない。
また今回何とか通過した734地点の降雪に関する参考情報。
前回3年前に通過した時は今回より積雪が多かった。
当時の記録では青森市内積雪0cmの翌日登山している。
今回は青森積雪0cmが25日なので11日後の登山となる。
このことから734地点の通過は青森積雪0の前が良いと推測。
(3) 体力について
冒頭で記した様に体力の衰えを昨年急に感じ始めた。
母親が高齢になると家事の負担が増えつつある。
一方で時間の使い方が下手でダラダラする事も多い。
結果的に以前より運動に費やす時間が減っている。
なので体力衰退要因の一つは運動量減少と考えた。
どうすれば効率的に体力維持できないか思考する。
運動では筋肉と肺活量が大きい要因なのではと考える。
筋肉や肺活量の衰えを減らす方法はないだろうか?
そこで日常の些細な場面で筋肉を意識し行動する。
例えば料理や歯磨き中でも少し踵上げ動作を加える。
肺活量の衰えを防ぐには腹筋を鍛える事を意識する。
例えば気付いた時だけでも腹筋に力を加える。
外で運動するだけが運動でないと考え日常に取り入れる。
未だ始めたばかりで効果の方は定かではない。
暫く続けて効果がある様ならまた記事にしたい。
4 時間経過
08:25 みちのく料金所手前
10:23 林道分かれ
11:00 標高628
11:46 三角岳 (休29分)
13:02 大毛無山 (休11分)
13:38 標高734 (匍匐通過8分)
14:41 標高465 (5分)
15:30 みちのく料金所手前
徒歩時間 6:10 (休憩45分除く)
徒歩距離 13km
5 旅の写真
8:27 みちのく有料料金所手前からスタート

8:31 橋を過ぎ除雪道路脇の雪山に左折

8:33 積雪1mほどの雪の上を歩く

8:35 所々で沢からの流水箇所では下り上りする

9:04 橋下を潜る所でも下り上りする

9:23 方向転換して沢を横切る

9:29 林道分岐では左側の林道を進む

9:35 毎年ほぼ同一地点で見る熊の足跡?

10:01 また方向転換し沢を横切る

10:08 カモシカの足跡風?

10:21 林道を分かれ右進し尾根を目指す

10:27 少し新雪のある斜面を進む

10:43 土の見える尾根を避け残雪のある所を登る

カモシカ2頭目撃
10:54 登った尾根を振り返る

遠くに八甲田連峰
11:03 行く手の稜線を見るとカモシカ一頭目撃

11:15 カモシカのいた崩落気味の稜線を振り返る

11:20 小ピークの右奥に三角岳を望む

11:25 右の小ピークを巻いて三角岳を目指す

11:43 三角岳直下の樹木に付着するミニ雪庇

11:47 三角岳山頂の反射板と八甲田連峰

12:19 三角岳から大毛無山(右奥)への縦走路

大毛無山(右)~小ピーク~734ピーク(左)の縦走路も眺望ー734頂上部は少雪
12:31 大毛無山へ向かう縦走路

13:05 大毛無山山頂から北西の眺望

13:05 大毛無山山頂から北東の眺望

13:14 大毛無山から南西へ向かう

13:31 734ピークは樹木上に何とか残雪あり

樹木上の積雪量が少量に感じられて雪崩落の恐怖
13:40 734ピークの雪の上を這いつくばり進む

13:56 734ピークを過ぎホッとして振り返る

14:06 八幡岳方面を眺めながら尾根道を進む

14:21 所々に小クラックが見られる

14:29 縦走して来た稜線道を振り返る

14:34 進行方向を眺める

14:39 進行方向を少し右に変える

14:51 徐々に地面が見え始める

15:05 最後の鉄塔地点では残雪は僅かになる

15:08 鉄塔保守の右折標識を無視し尾根を下る

15:18 尾根の終点には残雪が現れる

15:21 下りてきた尾根を振り返る(右側を下りた)

15:23 みちのく料金所裏手の残雪を進んで車に戻る
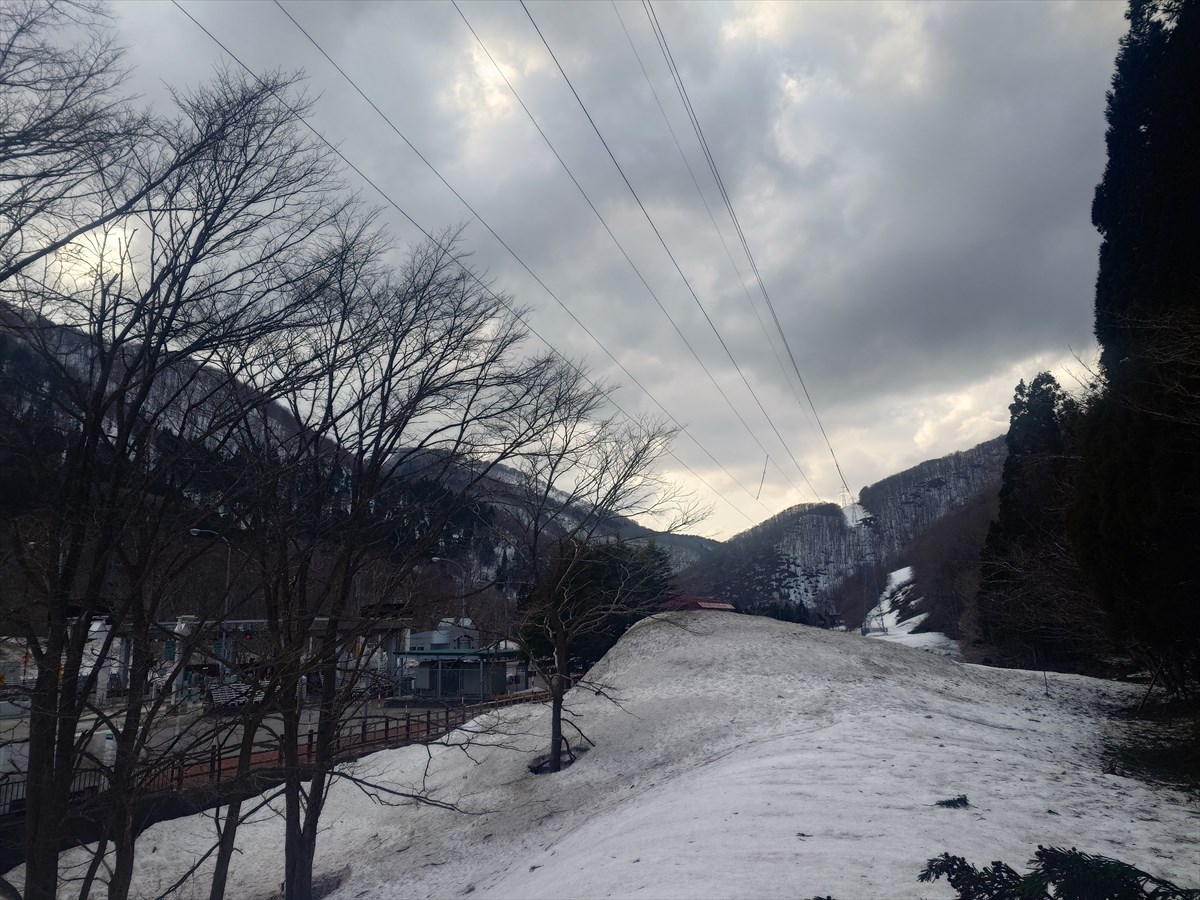
6 登山と歩行のルート図